こんにちは!現役ハンドメイド作家のミロクです。
普段はバッグやお財布をメインで作っています。
ミシンを始めるきっかけとして一番多い理由の一つは、幼稚園・保育園の入園グッズ作りではないでしょうか。
決められた期日までにバッグや巾着など何点も作らないといけないから、ハードル高く感じてしまいますよね。
私自身はこれまでに、息子の幼稚園と小学校、娘の幼稚園の計3回の入園(入学)グッズ作りを経験しました。
毎回、秋のうちから布を選び材料を揃え準備万端!
あとは縫うだけ!
・・・という状態で数か月放置し、実際に作るのは2月に入ってからでした(笑)

マネしちゃだめですよ~
今回は入園・入学グッズで必ず必要になる上履き入れの作り方です。
私のように期限ギリギリになってしまった人でも迷わず作れるように、実際の作業写真を交えながら詳しく説明しますね。
実際の作業は
- パーツはすべて長方形
- 縫うのはすべて直線
なので、初心者さんでも落ち着いて縫えばきれいに作れます!
基本的な作り方はレッスンバッグと同じなので、学校や幼稚園のバザー用にセットで作っても良いですね。
スポンサーリンク
上履き入れの基本サイズと材料
上履き入れの基本サイズ
学校や幼稚園・保育園によっては、細かくサイズが指定されている場合があります。
準備品についてのお知らせをよくチェックしてくださいね。
今回は一般的と思われる、こちらのサイズで作っていきます。

タテ28cm×ヨコ20cm×マチ3cmで作ります。
持ち手は24cmで作りましたが、お子さんに持たせた時に上履き入れが地面につかない方が良いので、長さは適宜調節してください。

マチというのは、袋物の厚みの部分です。
市販の上履き入れには、まったくマチのないぺたんこバッグもありますが、3センチ程度マチを付けてあげた方が扱いやすいです。
上履き入れの材料

上履き入れに必要なのは
- 表布(キルティングやオックスなど)
- 内布(薄手〜普通厚の布)
- 持ち手(①②と共布またはアクリルテープ)
- 持ち手を通すDカン
の4つです。
布の素材や色柄に指定があればそれに従ってください。
指定がなければ( )内を参考に好みの物を選びましょう。
↑私が使ったのはこの生地のピンクです。
とっても鮮やかなピンクで、遠くからでもよく目立ちます(笑)
↑内布は同じショップのこのチェック生地を使いました。
裁断・縫製ともに、とても扱いやすかったのでおすすめです!
持ち手について
持ち手は、市販のアクリルテープを使って作る方法と、共布を使って作る方法があります。
アクリルテープは必要な長さに切るだけですし、入園入学の時期になると色数も豊富に取り揃えてあるので、手に入る場合はそちらを使った方が簡単です。
「アクリルテープ」という名称が一般的ですが、「かばんテープ」「持ち手テープ」という名前で売っているお店もあります。
アクリルテープを買う時は、幅25ミリで、あまり固すぎない物を選びましょう。
(幅広&固いものだと子どもが持ちづらいです)
今回は、上履き入れ本体と同じ布(共布と言います)で持ち手を作る方法を紹介しています。
好みのテープが手に入らなかった時など参考にしてください。
持ち手を自作する時は、布用のボンドがあると便利です。

写真のボンドは「裁ほう上手」という商品です。
貼り合わせた上からアイロンで押さえると接着します。
アイロンが必要ないスティックタイプもありますが、かなりコスパが悪いので、チューブタイプをおすすめします。
ボンドがない場合は、待ち針やクリップを使いましょう。
↑裁ほう上手は縫わずにバッグが作れるくらい強度がある布用ボンドです。
手芸店や大きめのホームセンターなどにも置いてあると思います。
ショップによって値段に幅があるので、こちらのページで最安値をチェックしてくださいね。
→「裁ほう上手45g(チューブタイプ)」を楽天市場で探す
上履き入れの作り方 手順まとめ
記事が長くなるので、先に制作手順をまとめておきますね。
上履き入れの作り方は
- 生地を裁断する
- 布端の処理をする
- 持ち手・持ち手通しを作る
- 上履き入れ本体に持ち手・持ち手通しを付ける
- 表布と内布を合わせて袋口を縫う
- 脇を縫う
- マチを縫う
- 表に返して返し口を綴じる
- 袋口に仕上げ縫いをする
という流れになっています。
長そうに見えますが、布端の処理と返し口以外はミシンの直線縫いばかりなので、そんなに身構えなくて大丈夫です!
写真で解説!上履き入れの作り方
1.生地を裁断する
まずは必要なパーツを揃えましょう。
縫い代はすべて1センチでとります。(数字は縫い代込みのサイズです)
- 表布…タテ30cm×ヨコ22cm(2枚)またはタテ58cm×ヨコ22cm(1枚)
- 内布…タテ58cm×ヨコ22cm(1枚)
- 持ち手…タテ26cm×ヨコ5cm(表布1枚、内布1枚)またはアクリルテープ2.5センチ幅×26センチ(1本)
- 持ち手通し…タテ7cm×ヨコ5cm(表布1枚、内布1枚)またはアクリルテープ2.5センチ幅×7センチ(1本)
柄の向きに注意しましょう
バッグ本体パーツを裁断する前に、布の柄をよく見てください。
柄に上下がなくどちらから見ても変わらない物であれば、長く1枚で切れます。
反対に、柄に上下がある場合には、2枚に分けて切ります。

どうして分けちゃうの?
もし柄に上下がある布を長く1枚のパーツとして切った場合、半分に折ると、片側は柄が逆さまになってしまいます。
なので、2枚に分けて切り、底になる部分を縫い合わせて繋げる必要があります。

このように、布の表同士を合わせて(中表にする、と言います)、布の裏を見ながら底部分を縫い合わせます。
縫い代は1センチです。

こちらは底同士を縫い終わって表から見た写真です。
中央の縫い目を境に、柄の上下が逆転しているのがわかりますか?
これで、半分に折ってもそれぞれの面で正しい向きの柄が出ます。
縫い合わせる分、余計に縫い代が必要になるので、1枚の時と2枚の時ではタテの長さの合計値が違います。
※内布に柄の向きがある布を使う時は、内布も2枚に分けて切ってくださいね。
寸法は表布のサイズを見てください。
スポンサーリンク
2.布端の処理をする
パーツを裁断したら、布の端にほつれ止めをします。

ミシンの「ジグザグ縫い」または「ふちかがり縫い」で、布の端を縫っていきます。
(写真は家庭用ミシンのふちかがり縫いです)
ロックミシンを持っている人は、もちろんそちらを使った方がきれいに仕上がります。

ミロクさん、ロックミシン持ってるのに使わないの?

作業机にミシン2台置くスペースがないので…。
3.持ち手・持ち手通しを作る
共布を使った持ち手の作り方です。
表布を4つ折りにして作るのもよいですが、せっかくなので、表布・内布の両方を使って作ってみましょう。
3-1.布を中心線に合わせて折る

持ち手の幅を二等分します。
今回は布幅5センチなので、端から2.5センチのところに線を引いてください。

今引いた線に合わせて端を折ります。
中心で突き合わせるような感じです。
キルティング生地は厚くてアイロンで癖をつけにくいので、布用ボンドで仮止めしておくと良いでしょう。
表布2本に続き、内布も同様に作業します。
こちらは薄いのでボンドはなくても折れるはずです。
内布は、表布より若干細め、布同士が少し重なるように折るのがポイントです。
3-2.表布と内布を重ねて縫い合わせる
次に、今作った表布パーツと内布パーツを重ねます。
写真のように、布端が見えている方同士が内側になるように合わせてください。

前の工程で内布を少し細めに作ったので、表布が両側すこしずつ出ている状態です。
ここでも、布用ボンドで仮止めしておくと扱いやすいです。
もちろん待ち針やクリップでも大丈夫ですが、ずれないように注意しましょう。
仮止めしたら、両端にステッチをかけて固定します。
縫い目が内布から落ちてしまわないように注意しながら縫いましょう。

これで上履き入れ本体と同様に、表と裏で柄の違う持ち手ができました。

見栄えもするうえに、適度な厚みと柔らかさがあって、子どもでも持ちやすいですよ。
この方法は一度覚えておくといろいろな袋物で活躍しますので、ぜひ試してみてください。
【持ち手通しの作り方】
持ち手と同じ作り方で、持ち手通し用に短いバージョンも作ります。

Dカンに通して、できる限りキワを縫います。
(離れたところを縫ってしまうとDカンがグラグラします)
写真のようにファスナー押さえを使うのがおすすめです。
4.上履き入れ本体に持ち手・持ち手通しを付ける
4-1.名札やワッペンなどはあらかじめ付けておく
バッグに名札を縫い付ける必要があったり、タグやワッペンなどで装飾をしたい場合は、持ち手を付ける前のこの段階で付けておきます。
4-2.持ち手を配置する
装飾などすべて付け終わったら、持ち手を付けます。

持ち手を2つ折りにし、表布の袋口中央に持ち手の中心を合わせて置きます。(写真参照)
反対側の袋口中央には持ち手通しを同様に仮止めします。
出来上がり線より上側、端から5~7mmのところを2往復程度縫ってください。

布が重なって厚くなっているので、ミシンはゆっくりと動かしましょう。
5.表布と内布を合わせて袋口を縫う
持ち手を縫い付けた表布の上に、内布を中表に(布の表同士が内側になるように)して重ねます。
ずれないように固定したら、袋口(上履き入れ本体の短辺側。持ち手が付いているところ)を縫い代1センチで縫います。

写真の赤いラインを縫います。
下にある持ち手を縫いこんでしまわないように気を付けましょう。
6.脇を縫う
6-1.袋口が中央にくるように折る
袋口を両方とも縫ったら、袋口の縫い目同士を合わせて中央にくるように、下の図のようにたたみ直します。

さきほど縫った部分が真ん中になり、それを挟んで片側は表布、もう片側は内布になります。
6-2.返し口を残して脇を縫う
次にバッグの脇を縫います。
縫うのは下の図の青い線の部分(布端から1cm)です。

このとき、内布側に1か所、返し口を作ります。
底に近い部分はこの後マチを作るので、内布の真ん中あたりに返し口をとります。
図の赤い部分は10~15センチくらい縫わずに開けておいてください。
スポンサーリンク
7.マチを縫う
次はマチです。
バッグの角に当たる部分を写真のように三角に折り開きます。

写真の真ん中にある縫い目が、一つ前の工程で縫った脇線です。
この真下に底のラインがあります。
脇線を中心に左右に1.5センチずつ、計3センチの線を引き、そこを縫います。
左右対称になるように形を整えてから縫ってくださいね。
縫い終わったら、縫い代1センチを残して、先端の三角は切り落とします。
(ひっくり返すときジャマになるので)
切り口はジグザグミシンなどをかけてほつれ止めをしておきましょう。

表布2か所、内布2か所の計4か所を同様に処理してください。
8.表に返して返し口を閉じる
返し口から手を入れて布をつかみ、少しずつ引っ張りながら全体をひっくり返します。
返し口が裂けないように、丁寧に引き出します。
返し終わったら形を整えてから、返し口を縫って閉じます。

手縫いで閉じるときは、写真のように「コの字」に閉じていくと、縫い目が見えなくなってきれいです。
ミシンで閉じるときは、布の端1ミリくらいのところを縫えば目立ちません。
9.袋口に仕上げ縫いをする
最後に、内布を上履き入れ本体(表布)にきれいに収め、袋の口をぐるっと一周ミシンで縫います。
縫い代を落ち着けてバッグの口をきれいにしたり、補強の意味もあります。
以上で、上履き入れの完成です!お疲れさまでした。

まとめ
今回は、入園・入学グッズに必須の上履き入れの作り方手順を写真付きで解説しました。
文字にすると長く感じますが、
- パーツはすべて長方形
- 縫うのはすべて直線
なので、実際に作業すると、意外と簡単です。
布地やサイズを変えるだけで幼児~大人用まで対応できるので、一度覚えればいくつでも作れますね!
今回は共布で持ち手を作る方法を紹介しましたが、途中にも書いた通り、アクリルテープ(持ち手テープ)を使えば必要な長さに切るだけなので、さらに簡略化できます。
ぜひ挑戦してくださいね!
スポンサーリンク
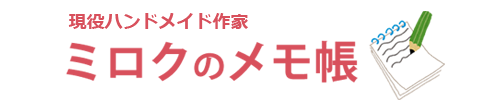






コメント